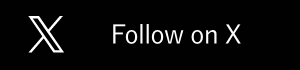提供:セイコーウオッチ
セイコーは2021年に創業140周年を迎え、これまで培ったヘリテージと新たな行く末を見定めるべくアニバーサリーモデルが多数登場する。そのひとつが「キングセイコー『KSK』復刻デザイン」だ。この新作はセイコーにとってどのような位置づけになるのか。腕時計Webマガジンの編集長・名畑氏と時計ジャーナリスト・篠田氏の対談を元に、世界に誇る国産メーカー・セイコーのブランド力を紐解いていく。
■1965年に発売された秒針規制機構を備えた2代目モデルのデザインを忠実に再現
「セイコー創業140周年記念限定モデル キングセイコー “KSK” 復刻デザイン SDKA001」(38万5000円)

1961年に誕生し、国産高級機械式時計市場を牽引した「キングセイコー」のヒストリカルモデルのシャープなケースやデザインを可能な限り再現。自動巻き。ケース径38.1mm、SSケース、5気圧防水、数量限定3000本
■腕時計に精通するふたりが、その歴史と行方を占う
ーー創業140周年を記念し復刻モデルが登場しますが、お二人のキングセイコーに対する印象は?

▲(左)時計ジャーナリスト・篠田哲生さん(右)Gressive編集長・名畑政治さん
篠田:まずセイコーといえば、グランドセイコー(GS)がメインだったんじゃないの?と思うのですが。
名畑:1881年、服部金太郎が服部時計店を創業したことに始まるセイコーだけど、グループにはさまざまな変遷があった。その過程で長野県の諏訪精工舎(現・セイコーエプソン)はグランドセイコーを、東京・亀戸にある第二精工舎(現・セイコーウオッチ)はキングセイコーを開発してきた経緯がある。この2大ブランドがセイコーのコレクションを支えてきたわけで、キングセイコーはセイコーの歴史を象徴するようなモデル。
篠田:同じグループ内に、ライバル関係みたいなものがあったんですかね(笑)。
名畑:スイス勢への対抗意識もあっただろうし、結果的に優れた時計を数多く生み出してきた。まあ切磋琢磨してきたのは間違いないだろうね。
ーーまさにセイコーの歴史を体現している、新生キングセイコーのポイントを教えて下さい。
篠田:元になった2代目に比べて日付けがつきましたね。

▲名畑氏も思い出深いと語る2代目モデル「キングセイコー “KSK”」が、今回の復刻ベースになっている。自動巻きの新モデルに比べて、当時は手巻き式だった
名畑:うん、あとはケースが1.4mm大きくなった。忠実に復刻していて違和感ないね。
篠田:だけどムーブメントは現代版ですし、過去のアーカイブをうまく利用したいい復刻モデルという印象です。
名畑:ケースの厚さも0.5mmしか大きくなってないし、よくこのサイズに収まったなと。僕のようなオールドファンから、新規ファンにもぴったりだね。

▲ボックス型サファイヤガラスの風防を採用。サイドから眺めると少しせり上がった、美しいガラスの曲線が見て取れる
篠田:しかも価格が適正だしグランドセイコーとはまた違った側面からセイコーの歴史を感じられる物語も持っているのが魅力的ですね。
名畑:そう、価格的に言えばこれをスイスが作ったら軽く100万円はするだろうね(笑)。
ーーディテールも美しく、特に12時位置のインデックスデザインは特徴的です。

▲多面カットを施した立体的なインデックスと堂々とした太く長い針も健在。12時位置のインデックスには特殊なカットが施されている
名畑:「ライターカット」と言うんだけど、細かな溝があって、スイスのお家芸。じーっと見ていると輝きが違う。2代目モデルから継承されているけど、当時このカットを成功させるのは苦労があったそうだよ。
篠田:セイコーにはそういうモノづくりの精神が継承されているのも素敵ですよね。海外でも人気で、そもそもムーブメントをクォーツ、メカニカル、スプリングドライブの3つを作れるメーカーなんてないですから。

Gressive編集長・名畑政治さん
1959年、東京都出身。85年からフリーライタとして活動をスタート。現在は時計専門Webマガジン「Gressive」の編集長を務める。

時計ジャーナリスト・篠田哲生さん
1975年、千葉県出身。雑誌『ホット・ドッグプレス』を経て独立。雑誌や新聞など多数媒体で執筆。近著に『教養としての腕時計選び』(光文社新書)がある。
▼名畑さん思い出の一本

▲キングセイコー、手巻きハイビートモデル「45KS」。後にオフィシャルクロノメーター検定に合格したモデルも発売。
■ディテール全てが美しい新たなキングセイコーの魅力

▲裏蓋にはキングセイコーのブランドアイコンである「盾」ロゴと、イエローゴールドカラーのメダリオンがオリジナルを彷彿とさせる

▲ダイヤシールドと呼ばれるセイコー独自の表面加工技術に、シャープかつエッジの効いたラグがモダンな印象を与えてくれる

▲ベルトには高級感あるクロコダイルを採用し、美錠はレトロかつ躍動感にあふれた「Seiko」ロゴを配しているのがポイント
■「日本の情景」をテーマにした140周年記念限定モデルが登場
ーーセイコーのサーガといえば、他にもさまざまなブランドがありますよね。
名畑:まず「プレザージュ」は有田焼、漆塗り、琺瑯、七宝と日本の伝統技術を採用するなど本当にコストパフォーマンスが高い。こんな価格で買えるのは、時計愛好家として本当にありがたいね。
黄金の針とインデックスが 暁の情景を想起させる一本
PRESAGE(プレザージュ)/140周年記念限定モデル
「Sharp Edged Series SARX085 メカニカル」(13万2000円)

▲日本の伝統的な、麻の葉紋様の型打ちを施したダイヤルに、シリーズ名の通りシャープなケースが特徴 。夜明けをイメージした「暁」がテーマだ。自動巻き、ケース径39.3mm、SSケース、10気圧防水、数量限定4000本
篠田:ただまだ歴史の浅いブランドですし、ストーリーという部分では今後に期待という印象ですかね。
名畑:たしかに。でも実際に現地取材も行っているけど、もっともっと語るべき職人さんの試行錯誤がいっぱいある。まあ逆に言えば、これからが楽しみなブランドと言えるかな。
篠田:あと世界初のGPSウオッチ「アストロン」は、セイコーのストーリーを背負ってますよね。ただGPSアンテナを使うためにケースの少サイズ化が難しいという側面もあります。
名畑:セイコーの大看板なだけにね。ただアンテナの形状やスペックにしても進化を続けているし、まさにGPSウオッチのエポックメイキングな一本。これからどういう変化をしていくのか注目するべきだね。
篠田:モジュールからすべてを自社開発してきただけに、次のビッグバンが起こる可能性のあるブランドですよね。
漆黒のケースに映える夜桜を表現したダイヤル
ASTRON(アストロン)/140周年記念限定モデル
「Global Line Authentic SBXC083 GPS ソーラー」(25万3000円)

日本が誇る “観桜” 文化から夜桜に着想を得たダイヤルを採用。情緒あふれる桜の舞う瞬間を紫のグラデーションとラメで表現している。GPSソーラー、ケース径42.7mm、SSケース、10気圧防水、数量限定1500本
ーー今回の記念モデルは「日本の情景」がテーマです。
篠田:メイド・イン・ジャパンのモノづくりをストーリーとしてプロダクトに活かせている好例だと思いますね。
名畑:そうだね、特に今回の「プロスペックス」は西表島をイメージしたグリーン文字盤。発色もいいし、日本の良さが伝わる。そもそもプロスペックスは価格帯の幅が広くて、手に取りやすいところから高級なものまでいろいろ。僕も1965年のファーストダイバーズを愛用してるし、素材違いとかダイヤルカラーとかバリエーションを増やしていってもらいたい。
篠田:プロスペックスはダイバ ーズ(海)が大半ですけど、空と陸もセイコーらしいシンプルな時計が出てきてほしい。
名畑:回転計算尺つきのパイロットウオッチとかは、実用的ではないしね。篠田くんが言うようにシンプルなGMTのモデルが出てくるとうれしいかな。
篠田:スマートウオッチとの差別化としても、所有感を満たしつつ削ぎ落とされた実用性こそ今後の腕時計の方向性かもしれないですね。
名畑:セイコーはありとあらゆる腕時計を作ってきた。「作ろうと思えばできちゃう」精神で、また素晴らしいタイムピースの誕生に期待しています。
西表島にインスパイアされた深緑が目に美しい3モデル
PROSPEX(プロスペックス)/140周年記念限定モデル
「MARINEMASTER PROFESSIONAL メカニカル SBDX043」(36万3000円)

▲岩手県・雫石の工場で作られる高性能キャリバー「8L35」を搭載。飽和潜水用防水を備えたプロフェッショナルダイバーズ。自動巻き、ケース径44.3mm、SSケース、飽和潜水用防水300m、数量限定3000本
PROSPEX(プロスペックス)/140周年記念限定モデル
「DIVER SCUBA 1968 メカニカルダイバーズ現代デザイン SBDC133」(15万4000円)

▲1968年発売モデルを現代的にリメイク。他2本と同様に、ダークグリーンの強化シリコン製替えストラップが付属する。自動巻き、ケース径42.0mm、SSケース、空気潜水用防水200m、数量限定6000本
PROSPEX(プロスペックス)/140周年記念限定モデル
「DIVER SCUBA ソーラークロノグラフ SBDL083」(8万9100円)

▲アウトドアでも使いやすいソーラー駆動で、カジュアルな格好にもフォーマルにも合う汎用性の高い一本。ソーラー、ケース径44.5mm、SSケース、空気潜水用防水200m、数量限定4000本
取材・文/三宅隆<&GP>、写真/江藤義典